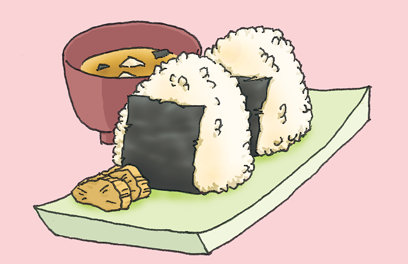
クラス替えして間もない頃、英語の授業で耳にした彼女の音読がびっくりするほど美しかった。あの瞬間の衝撃に勝る体験をわたしは今も知らない。それから10年が経ち、わたしたちは卒業と入学とを繰り返してから就職し、その間に何度か恋人も変わった。それでもふと思い出したように寄越す彼女の絵葉書が、わたしたちの関係を細々とつないでいる。
『帰国します』
知らせはいつも突然だった。なおは得意の語学を活かした仕事に就き、1年のほとんどは海外を飛び回っていた。迎えに来いとは書かないくせに、狭い絵葉書の裏面に帰国の日取りや着陸予定時刻が窮屈そうに並んでいるのは、彼女なりの甘えかたなのだろうと理解している。
消印はフランス、夕暮れの街路樹とエッフェル塔の写真。返信先の住所は書いてなかったけど、どうせ今から送り返しても間に合わない。そっと絵葉書を鼻に押し当てると知らない外国の匂いがした。
数日後、わたしたちは空港の到着ロビーに近い和食カフェで向かい合っていた。機内上映の映画が意外に面白かっただの、現地で買った服のサイズが合わなくて困っただの、久々の日本語でのコミュニケーションが楽しくて仕方がないようで、しばらくなんでもない話が続いた後、なおは話のついでのように、だけどどこか慎重に探るような調子で尋ねた。
「それで、まゆはなにか変わったことあった?」
ざっと思い返して、付き合っていた人との別れとかインフルエンザで寝込んだこととか、いくつかのイベントが頭をよぎったけど、結局いつも通りいちばん簡単な答えを選んでしまう。
「別に、なにも」
彼女はひとつ肩の荷を降ろしたように頷き、自分の近況を勢いよく語り出した。くるくる変わる表情に大げさなジェスチャー、そこにときおり外国語が混じるたび律儀な心臓がとくんと跳ねる。
「今度はどのくらい日本にいられるの?」
「3週間くらいかな。次の仕事の打合せとかあるけど、まあまあのんびりできそう」
今度はいつ帰ってくるの、と言いかけた言葉を飲み込んでしまう。聞いたってどうにかなるわけじゃない。はっきりしているのは、ひと月後にはもう日本に居ないということ。それをなるべくドライに受け止めようとしてやっぱりうまくいかないことも、久々の再会がちっともドラマチックじゃないことも、この10年で幾度となく繰り返されたお決まりの展開だった。
あの頃は毎日机を並べて授業を受けていたのに、気がついたらなおはずっと遠いところに飛んで行って、わたしは今でもあの時の鮮烈な記憶にしぶとく心を囚われている。
「なおはかっこいいね」
羨望と自虐が混ざった冴えないセリフに、彼女は不意に真面目な顔をした。
「あの時、まゆがそう言ってくれたから今も頑張れてるんだよ」
性懲りもなく高鳴る胸を無視して紅茶をすすると、なおは急におどけた表情になり、子どもみたいに手足をバタバタさせた。
「あー早くおにぎりが食べたい」
近くで終わった食器を下げていた店員が、眼鏡の奥で眼を細めている。
「もちもちの白いごはんにしょっぱい梅干しが入ってて、大きい海苔で包んであるやつ。あつーいお味噌汁をズルズルすすりながら食べたい」
「ずいぶん設定が細かくない?」
「だってずーっとずーっと恋しかったんだもん。夢にまで見ちゃった」
「この店にもあるよ、ほら」
なおは不満げに鼻を鳴らして、メニュー表の『おにぎりセット』の上に置いたわたしの指先をデコピンするみたいに弾いた。
「まゆの意地悪」
言外に匂わせた臆病な提案はあっさり却下された。
彼女のそんな無邪気や身勝手や思わせぶりな態度や、平気で海を飛び越えてゆく豪胆さと、メールアドレスも知ってるくせに絵葉書しか送れない気弱さに触れると、わたしは今もかすかな期待を抑えられない。
「まゆのおにぎりがいちばん美味しいんだもん」
懇願するようなだめ押しに、わたしは渋々な表情を見せつけながら立ち上がって伝票をつかんだ。
「じゃあ、梅干し買って帰りますか」
まゆは跳ねるように立ち上がり、交渉成立!と嬉しそうに笑った。
<了>
※そのうちイラストが入ります。


